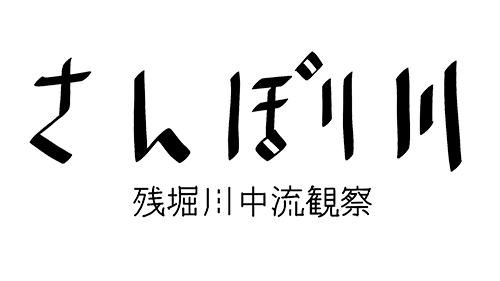残堀川は狭山池を水源とし、立川市柴崎町で多摩川に合流する全長14.5km、流域面積 34.7km²の川です。しかし、水源がはっきりと特定できているわけではなく、湧き水なの か、用水が流れ込んできたものなのかが未だに特定されていない不思議な川です。
特徴はなんといっても「堀だけが残る川」というように、頻繁に水が無くなってしまうところでしょう。
これは水源の水量の減少と、1982年の改修工事で礫層まで掘り下げてしまった事が原因だ と考えられています。その他にも、そもそもの地形が平坦なために川の流れが生まれない のも原因の1つだと考えられます。もともとは、氾濫対策のための改修工事だったため、どれだけ急激に水が無くなってしまったかが伺えます。
そんな「水が流れていない川」がなぜなくならないのでしょうか。その答えは雨天時にあ ります。武蔵村山市の方の残堀川に行くと河口付近で「増水時注意」という表示があちら こちらに見えます。これは大雨の時には川の水位が一気に増えるのです。その溜まった水は昭和記念公園近郊にある遊水池に水が引き込まれるそうです。
このように普段は川として機能していない川ではありますが、川の近郊に住む住人にとっては豪雨時の水害を防いでくれる大切な役割を果たしているのです。
そんな残堀川の歴史は今から数万年前、多摩川が立川段丘を作った時の名残だそうです。江戸時代に玉川上水が出来るまでは砂川三番の見影橋付近を通って、曙町2丁目、矢川へ と繋がり、青柳、谷保を抜けて府中用水に流れていたそうです。当時の川の長さは30 km、流域面積は約86km²。つまり今の川の2倍以上も大きな川だった事が伺えます。
そんな残堀川、東京都の西部を縦に流れている川は、非常に珍しいのです。